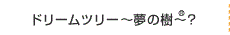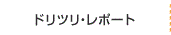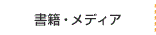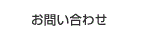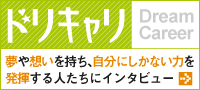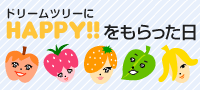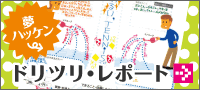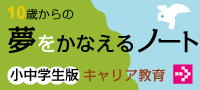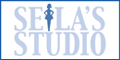011.描くことを選び続ける 2/3
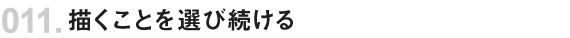
― ピンとくる感じ?
そうですね。絵を描き始める時は「あ、これを描こう」とピンとくることが多いです。 「これを描くことが今必要だ」とポッと・・・
― 衝き動かされて?
そうですね。
素材の力を借りながら、完成までに何カ月かを費やす、という流れですね。
作品はメッセージ、受け入れられないと成立しない
― 作品ができ上がった時はどんなことを考える?

ん~、これで伝わるかな~と考えます。
何かしら反省は残って、 「ここがやり足りなかったから、次はこうしたらいいんじゃないか」 みたいなものができて、それを次の作品として展開していくんです。
例えば、暗いトーンの作品ができると、 「こんなに暗いんじゃ、人は食いついて来ないんじゃないかな」と。 作品はメッセージ、人に受け入れてもらわないと成立しないものですから。
スケッチ=シナリオ

作品にはひとつひとつ、下書きとなるスケッチがあります。
スケッチは"道から外れた時に戻る場所"として欠かせません。
「自分は本当はこうしたかったんだ」と確認するという意味でも。
やっぱり、人は目に見えているものに振り回されてしまいますし、
道から外れたということがわかっても、どこに戻ればいいのかがわからなくなるんです。
混乱しちゃって。それで、それを確認するためにスケッチは大切です。
― 芝居でいうシナリオですね
そうです。
― アイディアが浮かばない時はどうしている?
踊ったりしていたことが・・・(笑)
それこそ、美大の卒業制作の頃は複数の仲間と同じアトリエで描いていまして、
立ちあがって踊り出したりして、「踊ってないで描け!」とか言われました。
― 今は?
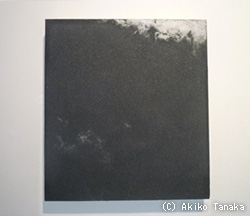
何か全く作品づくりと関係ないことをするのが多いですね。 もともとガーッと集中するというわけではありませんが 人がいると描けないタイプなので、人が寝静まった深夜になると描きやすいです。 本当にスランプになったりすると、たぶん、5分おきくらいに部屋を出たり、 入ったりしているかもしれません。
― 気持ちをスイッチするには?
音楽や本の力を借りて、「これが正しい道だよ」なんて言い聞かせます(笑)。
作品のアイディアの基になるのも展覧会や本、音楽だったりします。
こういう気分の時はこんな音楽、という定番もあります。
お酒の力はムリ!お酒は道を誤ることがありますから(笑)。
― 特に好きなのは?

ん~いっぱいありすぎて・・・最近も読み返しましたけど、子供のころ読んでいて
今、良いと思うのはミヒャエル・エンデとか宮沢賢治とか。
大人になっても影響を受けていますね。
子どもにもですが、わかりやすく書かれているのに大人にとっても謎を残すというところに惹かれます。
― 入り込んじゃうタイプ?

そうかもしれません。
わかって、納得してしまって終わり、というのは文学作品も含めて芸術作品にはない
と思います。
ビジネス書などとは違って良い作品には、時代を超えて何度も反芻(はんすう)して、
その都度、違う感覚を持てる耐久力を持っているものだと思います。
繰り返し甲斐のあるものが好きですね。