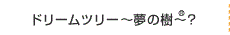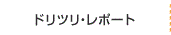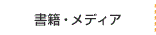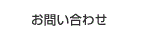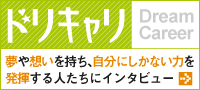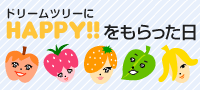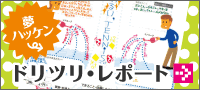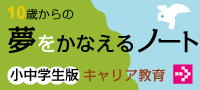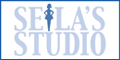006.株式会社ニッポンの仲間たちへ 3/4

株式会社ニッポンの仲間たちへ
― 辞めた翌朝、最初に考えたことは?
「いよいよ始まるな」わくわく感が大きくなった。
― 不安なし?

不安と不安じゃないの間を行き来するのは常でしょう。 だって、もしも、今話しているこのビルに鉄骨が落ちてきて大怪我するとか、 道を歩いていて突然車にはねられたらどうしようとか、 そういう不安は普段からあるものですよね。
線引きはいらない。生きている間、不安はついて回るものだし、 生きていればそれ以上の楽しみもある。 何かしらの不安はいつも感じている。それが生きているということなんだから。
例えば、入れ物にたくさんビー玉が入っていて 入れものが会社でビー玉は私たちだとする。 そのビー玉をテーブルの上にザーッと開ければビー玉が転がる。 会社を辞めるというのはそれだけのことでしょう。
つまりある場所が違うだけのこと。 コップの中なのか、テーブルの上なのかだけの違いでしょう。
「コップから出ちゃったー」と嘆かなくていいんじゃないのかな。 だって、ビー玉は、俺は、ここにいるんだから、命があるんだから、 活躍の機会はあるってことじゃない?
テーブルは社会であり、日本というこの国。テーブルから転げ落ちるのもあり。 そういう意味ではみんな「株式会社ニッポンの仲間」であることには変わりない。 そんな感覚ですよ。
実はこれ、バブル崩壊後、会社がシビアな状態にあった時に若手に話していたこと なんです。こう考えると、当時も口先だけでなく心底そう思って、言っていたんだ、 ということに気づきますね。
― サラリーマン時代と今とで違うことは?

それ、最近よく考えるんですけど、あんまりないですね。 自分を律して、ねじを巻きなおしながらやってきたから変わらないんですよ。
あえて言うなら、朝起きた時の気持ちかな。 サラリーマン時代は 朝起きて「これとこれをやらなくちゃな」 今は「今日って、あんなこともできるな」 でもって、 「やったー!嬉しい!」 そんな感じですよ。
・・・氏は以前、ビジネス誌に登場したことがある。 時はワーク・ライフバランス・ブームの走りで、当該特集で登場した。 "サラリーマンは公私を分けることはできない"というのがどこか当たり前だった当時、「ワークもライフも垣根がない」というスタンスを確立していて、 一歩も二歩も先を行くビジネスパーソンという印象があった。・・・
誰かが提唱しないといけないと思っていたんですよ。 だから、自分で声を上げたんです。
オンとオフがつながる感覚をなんとか味わってもらいたい。 そうすれば、まず、ビジネスパーソンが変わるし、 もっと言うと、ニッポンが変わると思う。
これはサラリーマンであるうちに言うべきだと・・・ 辞めてしまってからでは「そっちに行ったからできるんじゃないか」と言われてしまう。 だからこそ、社内でも言い続けました。 「できるんだ」という視点で考えて欲しいと、それが何かを救うような気がすると 思ったからです。
大量採用も大量リストラも起こるべくして起きた。 だから、俺は今ここにいる
― もし、ここに"職の神様"が降りてきて「東田、もうひとつ仕事をやっていいぞ」 と言われたら何をやりますか?
映画監督とか、映画カメラマンかな。 子どもの頃からカメラにものすごく興味があって、 小学生の頃、念願かなって母にカメラを買ってもらいました。 もう嬉しくて、嬉しくて。いつも持って歩いて色々なものを撮っていました。 焦点を充てて撮った写真を現像したら「写真って本当にきれいだな」と思ったし、 ロングや引き、アングルの違いで被写体が随分違って見えるんだということにも気づいて、 カメラの魅力の虜でしたね。
それが高じて、高校の文化祭では映画を自主制作して上映したんです。 撮影と監督を兼務して、出演者は同級生、舞台は校内、他愛もない内容でしたね。 当時は八ミリフィルムでしたから、撮影したフィルムをハサミで切って、 セロテープで貼ってと、アナログな作業で手がかかりましたが、 出来上がって、観てもらった時になかなかの反響があって、手ごたえを感じましたね。
自分が想いを込めたものが誰かを楽しませることができる。 お金を払って見てくれた人が評価する。単に笑っているだけでもいい。 人を喜ばせる仕事って素敵なことだと思いましたし、 自分のやりたい仕事を経験した気がしました。 実際、就職活動では映画製作関連やマスコミなども回りました。 そんな中でたまたまリクルートに当たってしまったんです。
自分の引き出しのひとつに出会ってしまったんですね。 リクルートには映画をつくる部署もありましたし。
人を喜ばせることがしたいというのと同時に、 人のために何かをしてあげたい、助けたい、という考えが頭にインプットされていて、 「自分は人のためになることをやるべき人間なんじゃないだろうか」と ずっと思っていました。 両親もそういう人でしたから、親譲りでしょうか(笑)
社内にいた時は今いる人たちの才能を引き出し、新しいものをいかに解き放つか、 そんなことを考えていました。
大量採用・大量リストラの両方を経験した後、 「俺、やろうとしていることと真反対にいるじゃない」とか、 そんなことを考えていた時期もありますが、今にして思えば、 起こるべくして起こったんだと思う。だから、今ここに自分がいるんだと思っている。