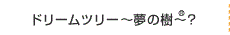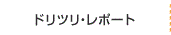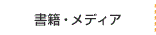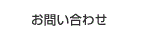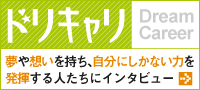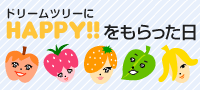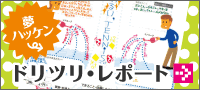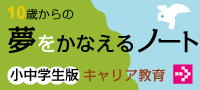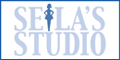012.天命づくりをすべし 2/3

― 司法試験突破=弁護士になるという夢が砕けそうになったことは?
ありません。
壁だとか、困難だとか思いませんでした。
司法試験を突破するためのゼミを組んだんですが、 普段ほとんど勉強していないから、いざ、ゼミに出たところで 言っていることはさっぱりわからない。まるで外国語みたいに聞こえて、 ゼミ中で一番、出来が悪かったんです。 もうついていくのだけで精一杯。

だけど、聞いているうちにだんだんわかってきました。 私は全体像から掴む質なので、 民法の話をしている時に、「刑法とはどう違うんだろう」と考える。 「憲法との概念の違いは?」と考えるから、細かい議論にはついていけませんし、 わかりません。 ただ、法学概論とか法論理学を学んだ時に演繹法※とか帰納法※が頭に入っていて、 大枠で捉える習慣がついていたんです。
※帰納法:具体的事実から抽象的な構図をつかむ
※演繹法:全体構造から具体的事実を位置づける
自分には演繹法が合っていると思ったので、法律を解釈する時に憲法から入って、
民法、刑法が、民法の下に民事訴訟法、刑法の下に刑事訴訟法がある。
その体系を始めから自分の頭の中に置きました。
例えば、みんなが議論している時に「今、どこの話をしているのか」ということを
常に考えていたんです。
すると、ある時、ポンと具体的な問題が弾けた時に頭に入ってきました。
法律周辺学が効きました。
「キミは受かるよ」
― 言わば、司法試験と直接関係のないことから始めたのはなぜですか?

安保闘争が大きかったと思います。
悪法は法か?という問いに対してどんな態度を取るのか、という議論や
憲法から見た日米安全保障条約の解釈、
日米安全保障条約は従属的な内容を含む悪法だとみるか?条約と憲法の優劣、
そんな中で憲法が支配されることはないという考えを持ちました。
『正義』は圧倒的な価値基準でした。
一方でわかるようにならない、できるようにならない自分がいて、
ある時、思い悩んで先輩に相談したことがありました。
「政治を志した方がいいのか」と漏らしたんです。
すると、
「キミは受かるよ」
先輩はそう言ってくれました。 いつもペケなのに、すごい励みになりました。
そういうことがいかに大切か。子どもにとって、そう言ってくれる人が必要です。
成績だけを見て決めるのではなく、「キミはこの点が優れているよ」と
言ってくれる"先生"が必要です。
私はそれ以来、人を否定的に評価しなくなりました。
否定的に評価するのはその人にとっての打撃。
たとえ冗談でもあってもならない。今以ってそのことは守っています。
もう亡くなっていますが、その先輩のお陰だと思っています。
あの時、先輩の言葉がどんなに嬉しかったか、どれほど励みになったことか。 それからグングン成績が上がって、みんなより先に司法試験に受かりました。 最初の挑戦で受かりました。困難と意識したことはありません。
勉強法は自分で編み出して、 司法試験は7科目ありますが、それを最小限のテキストに当てはめると 1万ページにあたる。その1万ページを7回読もうと決めました。 7回読むためには1年に何ページ読めばいいかと計画を立てる。 1時間なら、1日なら、1ヶ月なら何ページ読まないといけないか目標から逆算して 計画立てる。それを当時からやっていたんです。